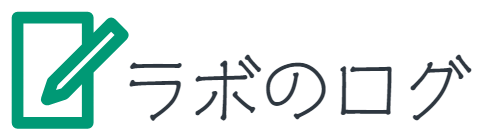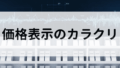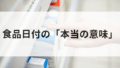「新発売」のシールや、「新しくなりました!」という言葉に惹かれて、つい商品を手に取ってしまうこと、ありますよね。
でも、家に帰って使ってみて、「あれ…これ、前のと何が違うんだろう?」と、首をかしげた経験はありませんか?
かつて商品部にいた頃、新旧たくさんの商品データを見てきて感じたのは、商品の「新しさ」には、実は色々な段階があるということです。
この記事では、そんなお買い物の小さなモヤモヤを解消するために、パッケージが変わった商品が「本当に新しくなったのか」を見分けるための、3つの具体的な視点を、元商品部の経験からお伝えします。
この視点を知ることで、広告やパッケージの雰囲気に惑わされることなく、ご自身にとって本当に価値のある選択ができる、小さなきっかけになれば嬉しいです。
そもそも、なぜ「パッケージだけ」変えるの?

店頭で「お、新しくなってる」と気づいてもらうことは、商品が生き残り続けるためにとても重要です。
とはいえ、商品の成分や中身を根本から改良するのは、私たちが想像する以上に時間もコストもかかる、大きなプロジェクトになります。

どんなに中身が良くても、まずは手に取ってもらえないことには売上につながらない
一方で、パッケージのデザイン変更は、比較的少ない負担で商品の「鮮度」を上げるための有効な手段。
商品部にいた頃も、こうしたデザイン変更のデータは頻繁に目にしました。
- 売上のテコ入れ:少し売れ行きが落ち着いてきた商品の注目度を、改めて高めたいとき。
- 季節感を出すため:春には桜、秋には紅葉のデザインなど、季節限定のパッケージで特別感を演出したいとき。
- 表示の変更に合わせて:法律の改正などで、成分表示などを変更する必要が出たタイミングに合わせて、デザイン全体をリニューアルするとき。
決して手抜きという訳ではなく、商品を皆さんの元に届け続けるための、作り手側の工夫の一つなのですね。

最近はアニメとのコラボ等でコレクション性の高いパッケージデザインもありますね♪
では、私たちはその「工夫」の裏側を、どう見分けていけば良いのでしょうか。
元商品部が教える、見分け方の3つの視点

誰でも簡単に実践できる、具体的なチェック方法を3つご紹介します。
この視点を持つだけで、商品の本当の姿が少しずつ見えてくるはずです。
視点1:パッケージの「言葉」に注目する
まずは一番簡単な方法です。
パッケージに書かれている言葉を、少しだけ注意深く見てみましょう。
もし中身に重要な変更が加えられている場合、企業はそれを積極的に伝えたいはずです。
そのため、「新処方」「新配合」「〇〇(成分名)アップ」といった、具体的な言葉が使われていることが多くなります。
一方で、デザインの変更が主である場合は、「新デザイン」「新パッケージで登場」といった、中身の変更には直接触れない表現が選ばれがちです。
ほんの少しの違いですが、ここには企業の意図が表れています。
視点2:公式サイトの「ニュースリリース」を確認する
「この変更、なんだか重要そうだな」と感じたら、企業の公式サイトを訪れてみるのが確実です。
特に「ニュースリリース」や「お知らせ」といったページには、信頼できる情報が載っています。
なぜなら、企業はこうした公式発表の場では、誤解を招くような曖昧な表現を避けるからです。
商品のリニューアルが、具体的にいつからで、何が、どのように変わったのか。
もし本当に中身が進化したのであれば、その開発背景やこだわりが、きちんと文章で説明されているはずです。

ニュースリリースは、皆さんに知ってほしい情報の集合体!
お店で気になったら、スマートフォンでさっと企業名を検索してみる。
その一手間が、確かな選択につながります。
視点3:バーコード(JANコード)を比較する
少し専門的になりますが、これは私が商品管理の現場で常に見てきた、最も確実な方法の一つです。
商品の裏側についている、バーコードの数字を見てみてください。
この数字(JANコード)は、いわば商品の「戸籍」のようなもの。
「どの事業者の、どの商品か」を識別するための、世界共通の番号です。
そしてここには、「中身の仕様が少しでも変われば、新しい番号を取得しなくてはならない」というルールがあります。
つまり、前の商品とJANコードが同じであれば、それは「中身は同じ商品」である可能性が非常に高いということになります。
もしお店で迷ったら、前に買った商品のパッケージ写真が残っていれば、バーコードの数字を見比べてみるのも一つの方法です。
小さな「なぜ?」が、賢い選択のはじまり

今回は、パッケージだけが変わった商品を見分けるための、3つの視点についてお話ししました。
- パッケージの「言葉」に注目する
- 公式サイトの「ニュースリリース」を確認する
- バーコード(JANコード)を比較する
パッケージ変更の裏側にある企業の事情を知り、こうした視点を持つこと。
それは、単に商品を見分けるテクニックというだけではありません。
日々の暮らしの中で「これって、どうしてだろう?」と、ふと立ち止まって考えてみる。
その小さな好奇心こそが、溢れる情報に流されることなく、自分らしい豊かな選択をするための、大切な第一歩なのだと感じます。
この記事が、明日からの買い物を少しでも楽しく、確かなものにするための、小さなきっかけになれば嬉しいです。