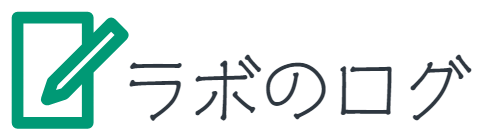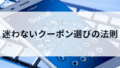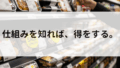スーパーで見かける「2個で○○円」「よりどり3点」といった言葉。
お得に感じて、ついカゴに入れてしまったけれど、後から「本当にこれ、必要だったかな…」と冷蔵庫の前で少しだけ後悔した経験はありませんか?
限られた時間とお金の中で、少しでも賢く買い物をしたい。
そう思っているのに、魅力的なキャッチコピーに心が揺らいでしまう。
「選択疲れ」を感じている方も少なくないかもしれません。
この記事では、かつて商品部のデータ管理担当として、数々の商品の「裏側」を見てきた視点から、なぜこうした「まとめ買い」を促す販売方法があるのか、その仕組みを解説します。
そして、その仕組みを知った上で、「お得感」に流されずに本当に自分に必要なものだけを選びとるための、具体的な思考法をお伝えします。
この記事を読み終える頃には、日々の買い物が少しだけクリアに見えるようになり、自信を持って「選ぶ」ことができるようになっているはずです。
お店の「お得」には理由がある。元商品部が見た「まとめ買い」の裏側

なぜお店は、商品を複数個買うと「お得」になるような売り方をするのでしょうか。
その背景には、お店側のしっかりとした戦略や、時には切実な事情が隠されています。
一つは、お客様一人あたりの購入金額(客単価)を上げるというシンプルな狙いです。
単品なら1つしか買われなかったかもしれない商品も、「複数買うとお得ですよ」と提案することで、「じゃあ、もう1つ」と手を伸ばしてもらいやすくなります。
そしてもう一つ、特に重要になるのが「在庫のコントロール」という視点です。
私が商品部で主に担当していたのは、弁当、パン、惣菜といった消費期限が非常に短い「日配(デイリー)商品」でした。
これらの商品は、まさに時間との戦い。
売れ残りは、そのままお店の損失に直結してしまいます。
そこでよく見られるのが、「よりどり2個で300円」といった、お客様自身が好きな組み合わせを選べる形式のセールです。
商品データを見てきた立場から言うと、この「よりどり」の対象となる商品群には、お店側の意図が反映されていることがあります。
例えば、定番で人気のパンに加えて、新商品や、販売期間がもうすぐ終わる季節限定のパンを意図的に含めるのです。
そうすることでお客様に新しい味を試してもらうきっかけを作ったり、在庫を効率よく動かしたりする狙いがあります。
これは、お客様にとっては選ぶ楽しみがあり、お店にとってはフードロスを減らせる工夫です。
ただ、私たち買う側が知っておきたいのは、その選択肢の中には、お店側の「売りたい理由」がそっと含まれていることがある、という事実です。
「お得感」に流されない。私が実践する3つの心の中の問いかけ
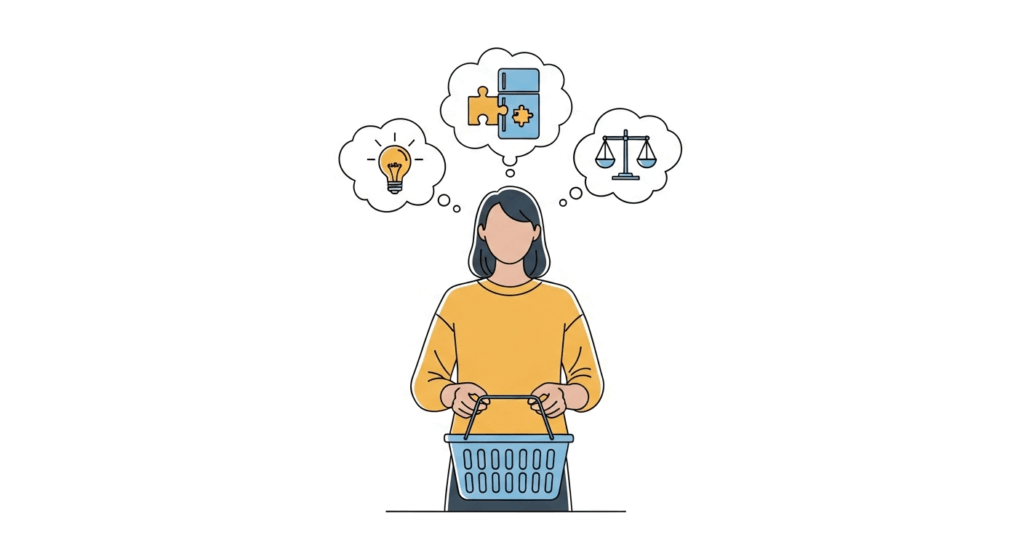
お店の仕組みがわかっても、いざ目の前に「お得」な商品があると、心が揺らぐこともありますよね。
そんな時、私は買い物をしながら、自分に3つの質問を投げかけるようにしています。
この習慣のおかげで、衝動買いがぐっと減り、買い物の満足度が上がるのを感じています。
問いかけ1:「もし、これが単品だったら本当に欲しい?」
「複数買うとお得」という言葉は、私たちの判断に魔法をかけてしまいます。
その魔法を解くのが、このシンプルな質問です。
「よりどり」で選んだ片方のパンは、単品でも絶対に買いたいもの。
でも、もう片方はどうだろう?
「もしこれが定価で、一つだけ棚に並んでいたら、カゴに入れるかな?」と考えてみるのです。
答えが「No」なら、それは「お得感」に惹かれているだけかもしれません。
問いかけ2:「使い切る未来が想像できる?」
特に食品の場合、大切になるのが「最後まで美味しく使い切れるか」という視点です。
「この『よりどり』で選んだ惣菜は、今日の夕食と、明日の夫のお弁当に一品足せるな」。
そんな風に、食卓に並ぶ光景や、冷蔵庫に収まっている様子が具体的に想像できるでしょうか。
もし、想像が曖昧で「まあ、なんとかなるか」と感じるなら、要注意!
その商品は、冷蔵庫の奥で忘れられてしまう未来が待っているかもしれません。
問いかけ3:「節約になるのはお金?それとも、時間や心の余裕?」
「お得」と聞くと、私たちはつい「お金の節約」だけをイメージしてしまいます。
でも、本当の「お得」は、もっと広い意味で捉えることができるはずです。
例えば、数種類の野菜が入ったカット野菜。
単品でそれぞれ買うより少し割高かもしれませんが、調理の時間を大幅に短縮してくれます。
その結果生まれた時間は、子どもとゆっくり向き合う時間や、自分のためのひと休みに繋がるかもしれません。
それは、お金には代えがたい「お得」と言えるのではないでしょうか。
目先の数十円、数百円だけでなく、自分の時間や心の余裕という「資源」を節約してくれるか。
その視点を持つことで、選択の基準がより明確になっていきます。
あなただけの「お得」を見つける、これからの買い物術

今回は、「複数買うとお得」という言葉の裏側にある仕組みと、それに振り回されずに自分らしい選択をするための思考法についてお話ししました。
- お店の「お得」には、客単価アップや在庫コントロールといった理由がある。
- 「単品でも欲しい?」「使い切れる?」と自分に問いかけることで、冷静な判断ができる。
- お金だけでなく、時間や心の余裕といった視点で「お得」を捉え直してみる。
誤解しないでいただきたいのは、こうした「まとめ買い」の提案が悪ではないということです。
お店の戦略を理解した上で、「これは今の私にぴったりだ」と思えるものを選べば、それは日々の暮らしを助けてくれる賢い味方になります。
大切なのは、お店が作った「お得」の基準をそのまま受け取るのではなく、あなた自身の暮らしや価値観に照らし合わせて、「私にとっての “お得” って何だろう?」と考えること。
明日スーパーで「複数買うとお得」といった文字を見かけたら、ぜひ一度、ほんの数秒だけ立ち止まってみてください。
そして、心の中の問いかけをそっと試してみていただけたら。
その小さな習慣が、あなたらしい選択眼をみがく、はじめの一歩になるかもしれません。
そんな小さなきっかけになれば、とても嬉しいです。