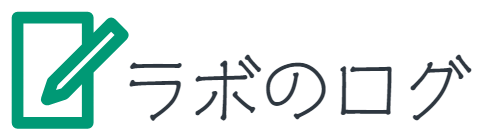スーパーのレジで、店員さんが商品のバーコードを「ピッ」とスキャンする光景。
私たちにとってはすっかりお馴染みですよね。
でも、あの縞模様と数字の羅列が、一体何を表しているのか、じっくり考えたことはあるでしょうか。
「ただの値段を読み取るための記号でしょ?」
そう思っている方がほとんどかもしれません。
実は、あのバーコードには、その商品が「いつ、どこで、誰によって作られたのか」という、いわば商品の『戸籍』とも言える大切な情報が詰まっています。
この記事を読めば、バーコードから商品の背景を読み解く簡単なヒントがわかります。
毎日のお買い物が少しだけ楽しくなり、目の前の商品を今までとは違う視点で見つめられる、そんな小さなきっかけになれば嬉しいです。
ただの縞模様じゃない。バーコードの正体は「世界共通の背番号」
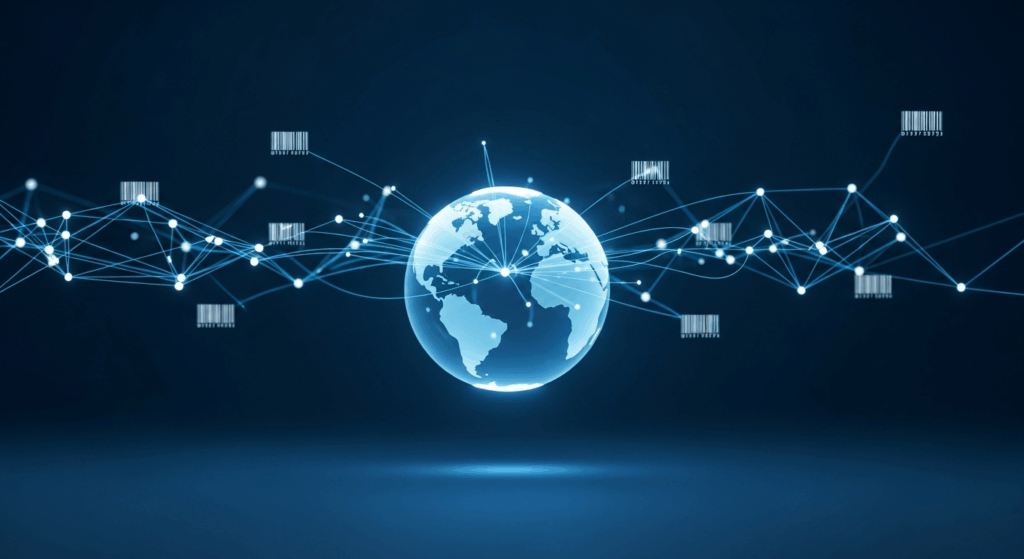
普段何気なく見ているあのバーコード、正式にはJANコードという名前がついています。
これは世界共通のルールで商品に割り振られる、いわば「商品の背番号」のようなものです。
この番号がないと商品の登録ができず、在庫管理も、売上の分析も始まりません。
それくらい、商品の流通を支える大黒柱とも言える存在なのです。
このJANコードは、大きく3つの情報から成り立っています。
- どの国の事業者か(国コード)
- どの事業者か(事業者コード)
- どの商品か(商品アイテムコード)
最後の1桁は、番号が正しいかをチェックするための数字です。
この13桁の数字があるおかげで、世界中のどこでも「この商品は何か」を正確に識別できる仕組みになっています。
【補足】お店で見るバーコード、実は2種類あるのをご存知ですか?
ただし、スーパーに並ぶ商品のバーコードは誰が印字したかという視点で見ると、実は大きく2つの種類に分けられます。
① ソースマーキング(メーカーが印字)

一つは、お菓子や調味料、日用品など、工場で完成された形で出荷されるほとんどの商品についている、お馴染みのJANコードです。
これを専門的にはソースマーキングと呼びます。
商品の情報源(ソース)であるメーカーが、出荷前に印字(マーキング)するという意味ですね。
② インストアマーキング(お店が印字)

そしてもう一つが、インストアマーキングです。
これは、私が主に担当していたお弁当やお惣菜、パンなど、お店の中でパック詰めされ、値段が付けられる商品に使われるバーコードです。
お店(インストア)で印字(マーキング)するため、こう呼ばれます。
こちらには、商品情報に加えて、その日の価格や重さといった、お店ごと・その時々で変わる情報が含まれているんです。
同じバーコードに見えても、メーカーが管理する情報と、お店が管理する情報とで、その役割や仕組みが使い分けられている。
この違いを知ると、商品の管理方法まで見えてくるようで、非常に面白い点だと思いませんか?
数字の「はじめの2桁」でわかる、商品の生まれ故郷

では、このJANコードから、私たちはどんな情報を読み取れるのでしょうか。
一番わかりやすいのが、最初の2桁(または3桁)の「国コード」です。
例えば、「45」や「49」から始まるバーコードは、日本の事業者が登録した商品であることを示しています。
普段買っている食品や日用品の裏側を見てみてください。
ほとんどがこの数字から始まっているはずです。
これを知っていると、例えば輸入食品コーナーで手に取った商品が、実は日本の企業が国内で管理・販売しているものだった、なんて発見があるかもしれません。
元商品部の視点から少し補足すると、これは「製造国」そのものを表すとは限りません。
あくまで「どの国の事業者がその商品を管理しているか」を示す番号です。
海外ブランドの商品でも、日本の法人が販売元として商品を管理していれば、日本の「45」や「49」が使われます。
この仕組みを知ると、商品のグローバルな流れが少し見えてきて面白いですよ。
商品の「裏側」を知ることが、賢い選択のはじまり

今回は、商品のバーコードに隠された情報についてお話ししました。
レジをスムーズにするための記号だと思っていたバーコードが、実は世界共通のルールで管理された「JANコード」という商品の背番号であり、そこから事業者の国籍まで読み取れる、ということがお分かりいただけたでしょうか。
もちろん、国コードを知ったからといって、すぐに何かが大きく変わるわけではありません。
でも、普段気に留めていなかった商品の「裏側」にある情報に目を向けることは、広告やパッケージのイメージだけでない、その商品の本質を見るための第一歩だと感じています。
次にスーパーで商品を手に取ったとき、ほんの少しだけ裏側のバーコードを眺めてみてください。
数字の並びから、その商品のささやかな物語が見えてくるかもしれません。
そんな小さな発見が、あなたの「選択眼」をみがく、一つのきっかけになれば嬉しいです。