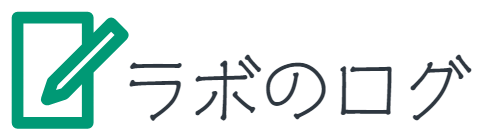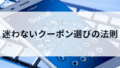最近は見かける機会が減りましたが、かつてコンビニの定番だった700円くじを覚えていますか?
レジで「あと○○円で引けますよ」と声をかけられ、つい予定になかったお菓子を追加してしまった…そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。
欲しい商品が当たれば嬉しい、あのワクワクするキャンペーン。
しかし、その裏側には非常に巧みな販売戦略が隠されていました。
この記事では、元商品部で販売の仕組みを見てきた私の視点から、まず「700円くじ」が当時どのような狙いを持っていたのかを振り返ります。
そして、時代の変化とともに、なぜその姿を消しつつあるのか、その本当の理由を紐解いていきます。
キャンペーンの裏側を知ることで、現在主流の「お得」との上手な付き合い方が見えてくるはずです。
データが語る「もう一品」の重要性。700円くじの戦略を振り返る

かつて、多くのコンビニで実施されていた「700円くじ」。
その最大の狙いは、単に客単価(お客様一人が一度に支払う金額)を上げることだけではありませんでした。
私が商品部のデータを見てきた観点からすると、より重要だったのは買い上げ点数、つまりカゴの中の商品を「もう一品」増やしてもらうことでした。
なぜなら、コンビニが本当に売りたい利益率の高い商品の多くは、レジ横の淹れたてのコーヒーやホットスナック、そしてお弁当やおにぎり、オリジナルのパンといった日配商品だからです。
700円の雑誌を一冊買ってもらうよりも、合計700円になるよう、おにぎりやパン、サラダなどを組み合わせて買ってもらう方が、お店にとってはるかに価値が高いのです。
そして「700円」という金額設定も絶妙でした。
当時のコンビニの平均客単価は500円~600円台。
お客様に「あと100円ちょっとで届く」と感じさせ、「それなら…」と利益率の高いレジ横の揚げ物や新発売のお菓子に手を伸ばさせる。
「700円くじ」は、お客様に損した気持ちにさせることなく、お店が売りたい商品を自然に買ってもらうための、非常によくできた仕組みだったのです。
なぜ『700円くじ』は姿を消しつつあるのか?時代の変化がもたらした理由

では、あれほど効果的だったキャンペーンは、なぜ姿を消しつつあるのでしょうか。
そこには、お客様の意識、お店の事情、そして戦略の進化という、複合的な理由が考えられます。
理由1:お客様の変化 ―「不確実」より「確実なお得」へ
節約志向が高まる中で、私たちはよりシビアに「お得」を判断するようになりました。
「何が当たるかわからない」という不確確実性よりも、「必ず1個もらえる」「確実に割引される」といった、目に見えて確実なメリットを好む傾向が強まっています。
現在の主流である「1個買うと1個無料」キャンペーンは、まさにこの心理に合致した戦略と言えるでしょう。
理由2:お店の事情 ― 効率化と衛生意識の高まり
キャンペーンの裏側では、お店のスタッフさんが煩雑な作業を担っています。
本部から送られてくる大量のくじの束を日ごとや時間帯ごとに振り分けるだけでも大変ですが、本当の勝負は当たりが出てからです。
すぐに渡せるよう、あらかじめレジ周りに景品をかき集めておくのですが、その準備がまず重労働。
そして、アイスや冷凍食品などが当たった場合は、その都度売り場まで走って商品を探しに行かなければなりません。
実は私もコンビニ店舗での勤務経験があり、その大変さは身をもって感じていました。
だからこそ、商品部で企画側に回ってからも、キャンペーンのオペレーション設計は特に重要な課題だったのです。
人手不足が深刻化する現代において、お店の負担を減らす、よりシンプルな販促が求められるようになったのです。
さらに、コロナ禍をきっかけに私たちの衛生意識は大きく変わりました。
不特定多数の人が同じ箱に手を入れ、くじを引くというスタイルが、お客様にとっても、お店側にとっても心理的なハードルとなったのです。
物理的な接触を避けられる「1個買うと1個無料」の引換券方式は、こうした時代の要請にも応える形でした。
理由3:戦略の変化 ―「誰にでも」から「あなただけ」への進化
私が商品部にいた頃と今で最も大きく違うのが、データ活用の進化です。
かつては「700円」という形で全てのお客様に同じアプローチをかけるのが主流でした。
しかし今は、アプリなどを通じて「パンをよく買うあなたには、この新商品の割引クーポンを」「甘いものが好きなあなたには、スイーツの無料クーポンを」といった形で、一人ひとりの購買履歴に合わせたアプローチが可能になりました。
企業にとって、より費用対効果の高い「あなただけ」への販促が主流となり、誰にでも同じ「700円くじ」が担ってきた役割は、徐々に新しい手法へと置き換わっていったのです。
キャンペーンの裏側を知り、自分らしい選択を

ここまで見てきたように、「700円くじ」は「ついで買い」を促す優れた販売戦略でしたが、
- お客様の求める「お得」の変化
- お店の効率化と衛生意識の高まり
- データ活用による販促の進化
といった時代の流れの中で、その役目を終えつつあります。
しかし、大切なのは、販促の形が変わっても、その裏にある「これを試してほしい」「これも一緒に買ってほしい」という企業の意図は変わらない、ということです。
この仕組みを知ることで、私たちは新しいキャンペーンを前にした時も、一歩引いて「これはどういう意図なのかな?」と考える視点を持つことができます。
その上で、自分にとって本当に価値があると感じれば、その「お得」を賢く利用すれば良いのです。
この記事が、日々目にするさまざまなキャンペーンとの付き合い方を考え、あなたらしい選択をするための小さなきっかけになれば嬉しいです。