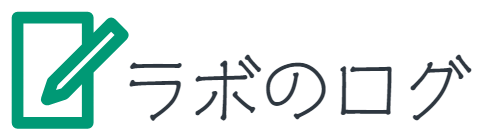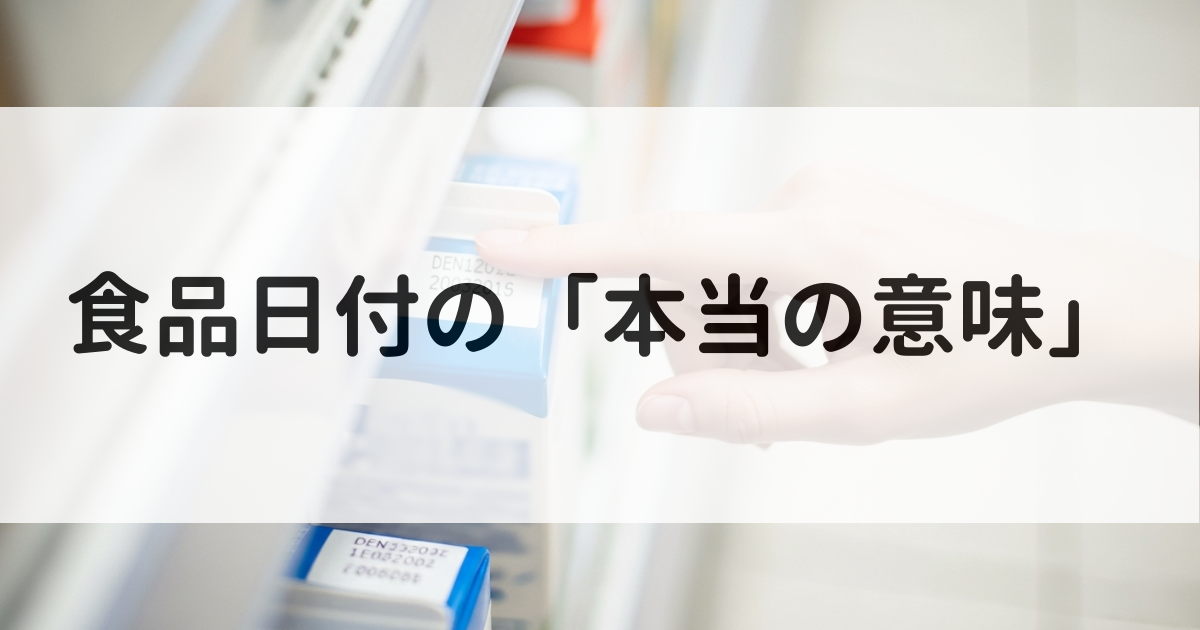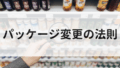スーパーで牛乳や食パンを手に取るとき、つい棚の奥に手を伸ばして、一番新しい日付のものを探してしまった経験はありませんか?
「少しでも長持ちするものを」という気持ちは、とても自然なことだと思います。
でもその一方で、「手前の商品を選んだ方がお店のためかな」「この一手間に、本当に意味はあるのかな?」と、ほんの少しだけ心がチクッとしたり、モヤモヤした気持ちになったりすることも。
この記事では、元々企業の「商品部」でデータ管理をしていた私の視点から、そんな食品の「日付」に隠された裏側を、そっとお伝えします。
読み終える頃には、日付を確認するときの小さな罪悪感や疑問がスッキリ解消され、あなたにとって本当に「心地よい選択」ができるようになっているはずです。
「製造日」が教えてくれる、商品の“ものがたり”

私たちが商品を選ぶとき、つい「賞味期限」や「消費期限」に目が行きがちですが、その前段階にあるのが「製造年月日」です。
これは、その商品がいつ、どこで生まれたかを示す、いわば「お誕生日」のようなもの。
すべての食品に書かれているわけではありませんが、この日付には大切な役割があります。
商品部時代は、お菓子や雑貨などを含めた全商品のデータ管理をしていましたが、特に工場との連携が密だったのが、お弁当のような消費期限の短い食品でした。
こうした商品のマスタ情報には、「製造してから何日で期限切れになるか」というような日数のルールを登録します。
一方で、実際の「製造日」や個々の「消費期限」は、工場側で商品ラベルやパッケージに印字され、専用の台帳で管理されていました。
つまり、商品部では「期限を決めるルール」を、工場では「ルールに基づいた個々の日付」を管理するという、役割分担があったのです。
こうした連携があるからこそ、万が一問題が起きても「いつ、どこで作られたものか」を正確に追跡し、素早く対応できる。
いわば、裏側のセーフティーネットです。
私たちが普段、安心して商品を手に取れるのは、こうした地道な仕組みが背景にあるからこそ、と感じています。
「期限」から読み解く、おいしさの“ピーク”

次に、私たちにとって一番身近な「賞味期限」と「消費期限」。
この二つの違いはご存知の方も多いかもしれません。
- 賞味期限:おいしく食べられる期限。これを過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではない。
- 消費期限:安全に食べられる期限。これを過ぎたら食べない方がよい。
この期限は、メーカーが科学的な検査に基づいて、安全と品質を十分に保証できる期間を設定しています。
そして商品がお店に並ぶ仕組みを見てきた観点から言うと、この「日付」は、販売の現場でも非常に重要なルールとして機能しています。
例えば、スーパーなどの小売店には「納品期限」というものがあり、「賞味期限の残り日数が〇日以上ないと納品できない」といった決まりが存在します。
また、期限が迫った商品を値引きして売り切る「見切り販売」のタイミングも、すべてこの日付が基準です。
特売品が安くなっている背景には、こうした「日付」を基準とした販売の仕組みが動いているのです。
それは、商品を無駄なくお客様に届けるための、裏側の工夫とも言えます。
「日付」を知れば、買い物がもっと“私らしく”なる

ここまで、食品の「日付」の裏側にある物語をお話ししてきました。
- 製造日は、商品の安全を守るための「生まれ」の記録。
- 賞味期限や消費期限は、おいしさや安全の「目安」。
この二つの意味を知ると、スーパーでの商品の選び方が少し変わってくるかもしれません。
もちろん、ご家庭での消費ペースを考えて、期限の長いものを選ぶのは賢い選択です。
ですが、「今日、明日中に使うもの」であれば、棚の手前にある商品を選ぶことも、また一つの素敵な選択なのではないでしょうか。
それはフードロスの削減につながり、お店にとっても、環境にとっても優しい選択になります。
日付は、私たちを縛るルールではなく、あくまで自分に合ったものを選ぶための「ものさし」の一つです。
その裏側にある仕組みや想いを知ることで、情報に振り回されることなく、日々の買い物を「自分らしい心地よい選択」に変えていく。
この記事が、その小さなきっかけになれば嬉しいです。