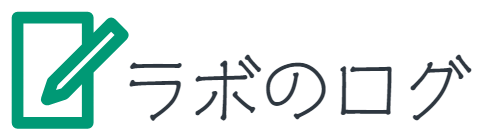「新発売」という赤いシール。
スーパーやコンビニでこの文字が目に入ると、なんだか特別なものに感じて、つい手に取ってしまうことはありませんか?
でも、ふと「この商品、いつまで『新発売』なんだろう?」と疑問に思ったことはないでしょうか。
「先週も見かけた気がする…」なんて思いながらも、明確な答えはわからないまま。
実は、その感覚はとても鋭いものかもしれません。
この記事では、かつて商品部で主に食品のデータ管理に携わっていた私が、スーパーなどで見かける「新発売」シールが貼られる裏側の仕組みについて解説します。
この記事を読み終える頃には、「新発売」という言葉に振り回されることなく、自分にとって本当に価値ある商品を落ち着いて選べるようになっているはずです。
多くの人が誤解している「食品の新発売」の定義

「新発売って、だいたい発売から1週間くらいかな?」
多くの人が、そんな風に漠然としたイメージを持っているかもしれません。
しかし、驚かれるかもしれませんが、特に私たちが日常的にスーパーなどで目にする食品において、「新発売」と表示していい期間について、法律などで定められた明確なルールは存在しないのです。

家電や化粧品など、製品によっては規定があるみたい
もちろん、あまりにも長い期間「新発売」と表示し続けると、消費者に誤解を与える「不当表示」として景品表示法に触れる可能性はあります。
しかし、「発売から○ヶ月以内」といった具体的な期間が法律で定められているわけではないのです。
結局のところ、「いつまで新発売とするか」は常識の範囲内で、商品を販売するメーカーやお店の判断に委ねられているのが実情です。
だからこそ、あるお店では早々に見かけなくなる一方で、別のお店ではしばらく新発売表示されたまま、という状況が起こるのです。
では、一体何を基準に「新発売」の期間は決められているのでしょうか?
そこには、私たちが普段目にすることのない、商品販売の「裏側の仕組み」が関係しています。
元商品部が見てきた「新発売」が決まる裏側の仕組み
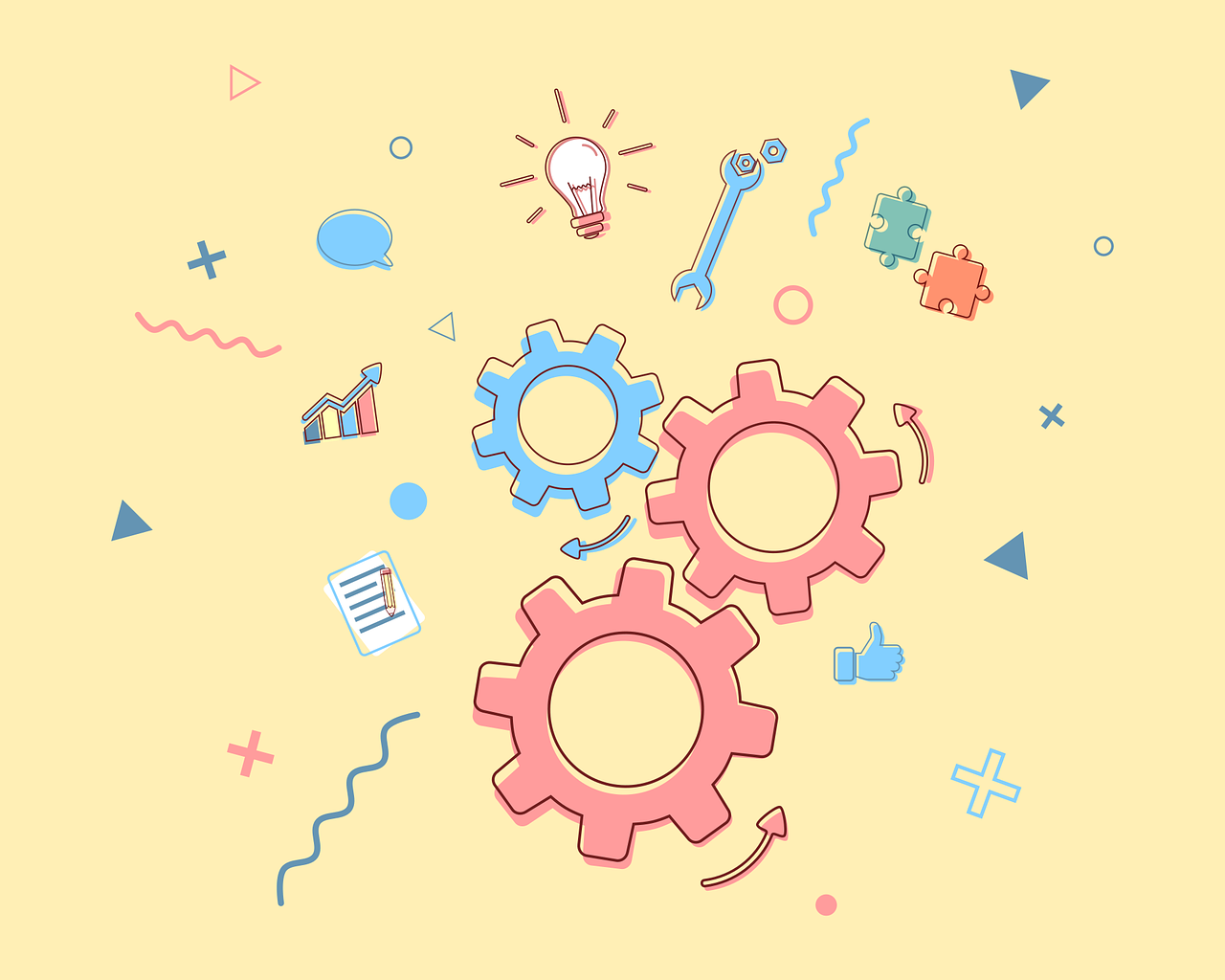
私が商品部に在籍していた頃、日々向き合っていたのは、次々と登場する食品がお店に並び、やがて姿を消していくまでの「データ」でした。
そのデータ管理の視点から見ると、「新発売」が決まる仕組みは、大きく3つの要素で動いています。
1. 「商品マスタ」のデータで制御されている
まず、すべての商品には「商品マスタ」と呼ばれる、いわば商品の戸籍のようなデータが存在します。
ここには商品名や価格と一緒に「発売日」が登録されています。
多くの企業では、この「発売日」を基準に、「発売日から2週間は『新発売』のアイコンを付ける」といったルールをシステム上で設定しているのです。
特に、私が主に担当していたお弁当やお惣菜といった日配商品は、商品の入れ替わりが非常に激しいため、この期間は1週間程度と、さらに短めに設定される傾向がありました。
一方で、この期間は商品の種類だけでなく、販売するお店の業態によっても大きく変わります。
例えば、毎週のように新商品が出て売り場が入れ替わるコンビニでは、店舗オペレーションの効率化のため、商品の種類にかかわらず「発売から1週間」など、チェーン全体で統一した短い期間を設定しているケースもあります。
2. 販促計画の一環ではあるものの、実態は「機械的」
「新発売」の表示は、もちろん商品を売り出すための販促活動の一環です。
ただ、実を言うと、小さなシールそのものよりも重視されていたのは、売り場の作り方でした。
一つひとつの商品にシールを貼るかどうかを細かく考えるよりも、「売り場をパッと見たとき、買ってほしい商品がすぐにお客様の目に留まるか」という、棚全体の構成の方がはるかに重要視されていたのです。
そのため、「新発売」の表示期間は、売上を最大化するために緻密に練られた戦略というよりは、むしろルールに沿って機械的に運用されているのが実情でした。
とはいえ、当時私が作成していた販売店向けの商品案内でも、特に力を入れて売り出したい商品については、「新発売POP掲示期間:○月○日〜○月○日」といった項目を設けることもありました。
これは、メーカーとして「この期間までは『新商品』としてしっかりアピールしてください」という販売店へのメッセージでもあるのです。
3. 「誰がシールを貼るか」で変わる
もう一つ、意外と知られていないのが、「誰が、どのタイミングで『新発売』の表示をしているか」という物理的な問題です。
例えば、お弁当やお惣菜のパッケージに最初から「新発売」と印字されている場合(ソースマーキング)、これはメーカー側で行われます。
特に、販路が特定の小売チェーンなどに限定されている商品の場合は、メーカーが自由に期間を決めているわけではなく、必ず小売店側と取り決めたルールに沿って、計画的に印字されています。
一方で、お店のスタッフが「新発売」の表示を追加する場合(インストアマーキング)は、現場の状況に左右されがちです。
商品パッケージを傷つける可能性があるため直接シールを貼ることは稀で、多くは値札の横に小さなPOP(販促物)を差し込む形でアピールされます。
このPOPを設置したり、期間が終わって撤去したりするのはお店のスタッフの仕事なので、忙しくて撤去を忘れてしまったり、逆に独自の判断で早めに外してしまったりと、お店によって対応にばらつきが出ることも少なくありません。

本当はルール通りに設置・撤去するべきだけど…
なかなか難しい時もあるよね
このように、「新発売」の表示期間は、システム、戦略、そして現場のオペレーションという複数の要因が絡み合って決まっているのです。
シールの「裏側」を知れば、選択はもっと自由になる

今回は、「新発売」シールが貼られる裏側の仕組みについてお話ししました。
この記事で最もお伝えしたかったのは、スーパーで見かける食品の「新発売」という言葉は、必ずしも商品の“絶対的な新しさ”を保証するものではないということです。
その裏側には、企業の販売システムや販促計画といった、ビジネス上の都合が大きく影響しています。
この仕組みを知ることで、私たちは「新発売だから」という理由だけで商品を手に取るのではなく、一歩立ち止まって考えることができるようになります。
「これは本当に今の自分に必要なものかな?」
「定番のあの商品と比べて、どんな新しい価値があるんだろう?」
そんなふうに、シールの言葉に左右されず、自分自身の目で価値を判断する。
その小さな視点の変化が、日々の食品選びや買い物をより賢く、そして自分らしいものに変えてくれるはずです。
このお話が、あなたがこれから商品を選ぶ上での、ささやかなヒントになれば嬉しく思います。