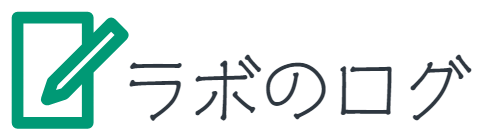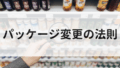スーパーの特売で買ったお気に入りのシャンプー。
数日後、ドラッグストアに立ち寄ったら「あれ、こっちの方が安い…?」なんて経験はありませんか?
見た目はまったく同じ商品なのに、お店によって、あるいはタイミングによって値段が違うと、「もしかして、いつも損してる?」「一番安いのはどこなの?」と、なんだか落ち着かない気持ちになってしまいますよね。
そのモヤモヤの正体、実は「お店の努力」や「仕入れ値の違い」だけが理由ではないかもしれません。
以前、ある大手企業の商品部で商品のデータ管理に携わっていた経験から、今回は商品の「戸籍」とも言える「商品マスタ」の視点で、同じに見える商品の値段が違うカラクリを、そっと紐解いていきます。
この記事を読み終える頃には、価格表示の裏側にある仕組みがわかり、日々の買い物で少しだけ心が軽くなるはずです。
見た目は同じでも中身は別人?商品の「戸籍」の正体

「同じ商品なのに」と私たちはつい考えてしまいますが、実は、お店のシステムの中では「まったくの別人」として扱われていることがほとんどです。
どういうことか、少し詳しく見ていきましょう。
まず、世の中のほとんどの商品には、人間でいうマイナンバーのように、国レベルで共通の番号が割り振られています。
商品パッケージの裏側にあるバーコードの数字、JANコードがそれにあたります。
これは、商品を作ったメーカーが設定する、いわば商品の“公式な”身分証明書です。
そして、このJANコードをはじめとした商品の情報が記録されているのが、商品マスタというデータベースです。
ここで少しややこしいのですが、この「商品マスタ」は、メーカーだけでなく、商品を販売するスーパーやドラッグストアなど、企業ごとにそれぞれが独自のものを持っているのです。

各企業や店舗ごとに品揃えが違うからね
各企業は、メーカーから仕入れた商品を、自社の「商品マスタ」に登録します。
その際、JANコードとは別に、社内だけで使うための商品コードという、独自の背番号のようなものを付けることもあります。
つまり、商品は「JANコード(全国共通のID)」と、お店ごとの「商品コード(社内だけの背番号)」という、2種類の番号で管理されていることがある、とイメージしてみてください。
これを踏まえて、先ほどのシャンプーの話に戻りましょう。
お気に入りのシャンプーがリニューアルされると、メーカーは新しいJANコードを設定します。
私たちの目には少しデザインが変わっただけに見えても、公式なIDが変わった「別の商品」として世に出されるわけです。
そしてお店側は、その新しいJANコードの商品を、自社の「商品マスタ」に新しいデータとして登録します。
結果として、商品マスタ上では、旧パッケージ品と新パッケージ品は、名前が似ているだけの「まったくの別人」として、はっきりと区別されるのです。
これは、
- 「今だけ10%増量」と書かれた期間限定品
- 小さなトリートメントのおまけが付いたセット品
なども同様です。
これらもメーカーが新しいJANコードを設定するため、お店のシステム上ではそれぞれが独立した「別の商品」として管理されています。
元商品部の視点から言うと、私たちが「商品」と呼んでいるものは、システム上ではこうした「コード」という数字の羅列でしかありません。
見た目がどれだけ似ていても、公式なIDであるJANコードが違えば、それは完全に「別のモノ」として扱われるのです。
だからこそ、「旧パッケージの在庫を売り切りたいから、少し安くしよう」といった価格設定が、店舗側で可能になるわけです。
なぜそんな面倒な管理をするの?データから見るお店の事情

「見た目が少し違うくらいなら、同じ商品として管理した方が楽なのでは?」と不思議に思いますよね。
なぜ、わざわざコードを分けて、面倒な管理をするのでしょうか。
その理由は、お店やメーカーが、商品をきちんと管理し、販売していくために不可欠だからです。
私が担当していたデータ管理や販促登録の視点から、主な理由を3つお伝えします。
1. 正確な在庫管理のため
もし旧品と新品を同じコードで管理してしまうと、「お店に、旧パッケージのシャンプーがあと何個残っているか」がデータ上わからなくなります。
正確な在庫を把握できなければ、次の発注計画も立てられませんし、旧品がお店に残っているのに、どんどん新品を送り込んでしまう、といった事態にもなりかねません。
2. きちんと売上を分析するため
「新しいパッケージに変えてから、売上は伸びただろうか?」
「おまけを付けた商品は、通常品より本当に売れたのか?」
こうした分析は、次の商品戦略を立てる上で非常に重要です。
コードを分けておくことで、どの商品が、いつ、どれくらい売れたのかを正確に追跡し、データに基づいた判断ができるようになります。
3. セール対象を間違えないため
実は、これが一番大きな理由かもしれません。
例えば、お店が「旧パッケージのシャンプー“だけ”を、在庫処分で30%引きにしたい」と考えたとします。
このとき、もし旧品と新品が同じコードで管理されていたら、システムは両者を区別できません。
セール設定をすると、お店に届いたばかりの新品まで30%引きになってしまうのです。
私が商品部にいた頃も、「この商品コードの旧品だけを、今週末のセール対象に」といった依頼が事業部から来て、システムに間違いなく登録するという業務がありました。
見た目が似ているからこそ、データ上で厳密に区別しないと、店舗もメーカーも意図しない販売をしてしまい、大きな混乱につながってしまうのです。
この地道なデータ管理が、店頭での適切な価格表示を支えています。
仕組みを知れば、もう迷わない。結局、私たちはどうすればいい?

ここまで、同じ商品に見えても、JANコードやお店の商品マスタ上では「別人」として管理されている、という裏側の仕組みをお話ししてきました。
きっと、ここまで読んでくださった方は、「なるほど、仕組みはわかった。で、結局、私たちは明日からどうすればいいの?」と感じているかもしれません。
この知識は、単なる豆知識ではありません。
それは、価格の違いに一喜一憂せず、あなたが「納得して」商品を選ぶための新しいモノサシになります。
具体的には、次の2つの視点を持って商品を選べるようになるはずです。
1. 「お得感」を重視するなら、あえて旧品を選ぶ
もしあなたが「少しでも安く買いたい」と思うなら、「パッケージリニューアル」や「在庫限り」といった言葉はチャンスのサインです。
これまでなら「古いから安いのかな?」と少し不安に感じたかもしれませんが、もう理由がわかります。
それはシステム上、売り切りたい「別の商品」だから。
品質が劣っているわけではなく、お店の在庫管理の都合であることがほとんどです。
パッケージの変更や少しの成分の違いが気にならないのであれば、旧品をあえて選ぶのは、仕組みを理解した人だけができる賢い節約術と言えるでしょう。
2. 「新しさ」を重視するなら、価格差に納得できる
一方で、「常に新しいものを使いたい」「リニューアル後の効果が楽しみ」という方もいるはずです。
その場合、新商品は発売直後、旧品よりも高く感じることがあるかもしれません。
しかし、その価格差は、新しい価値や機能に対するものだと納得できるのではないでしょうか。
「あっちの店では旧品が安かったのに…」と損した気分になるのではなく、「私は新しい価値を選んでいるんだ」と、自分の選択に自信を持つことができます。
このように、価格の裏側にある「違い」を知ることで、私たちは単に値段だけを比べるのではなく、「自分にとっての価値は何か」を基準に、主体的に商品を選べるようになります。
ぜひ、次回の買い物の際に、少しだけパッケージの表示を気にしてみてください。
「リニューアル」や「限定」の文字が、あなたらしい選択をするためのヒントをくれるはずです。
この記事が、あなたの暮らしの中で、そんな納得感のある買い物ができるきっかけになれば嬉しいです。